2025/04/08
大学広報を成功させるには?広報がうまい大学の成功事例を紹介
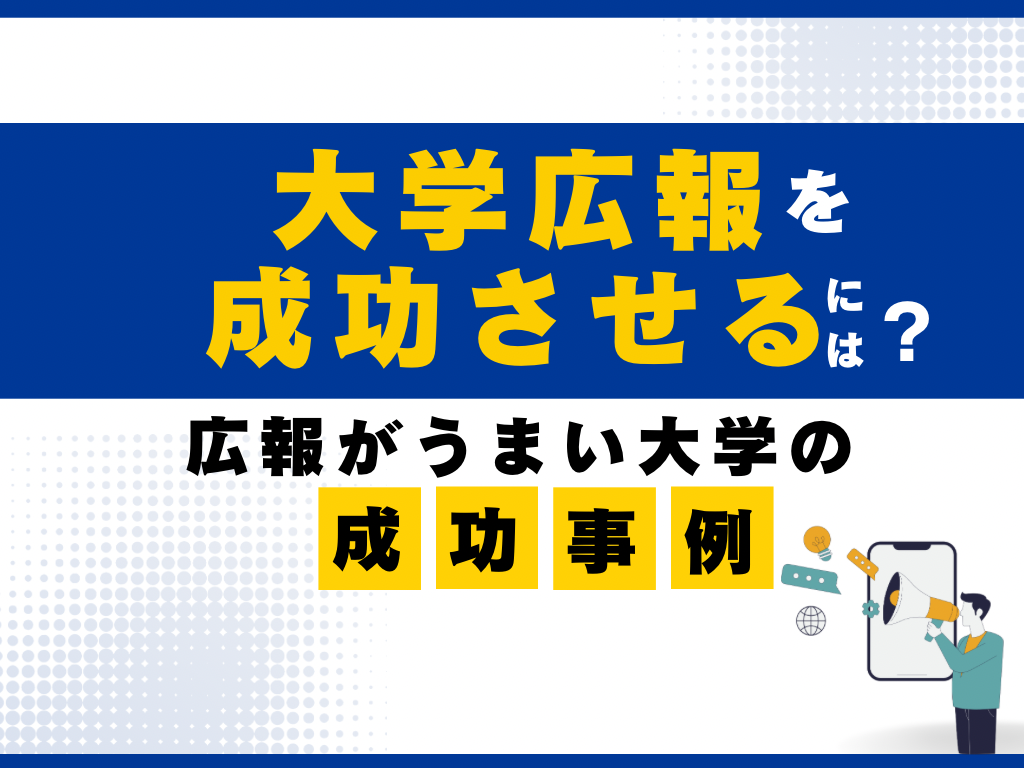
「大学の志願者を増やしたい!」
「どのような広報活動をすれば志願者が増えるの?」
「広報活動を成功させている大学を参考にしたい!」
このように考えている大学の広報担当者の方へ向けて、今回は大学広報を成功させるための方法について解説していきます。
広報戦略のポイントや広報がうまい大学の成功事例について解説するので、ぜひ参考にしてください。
これからの大学広報に必要なことは?
少子化の進行や大学数の増加によって、大学は学生を「選ぶ」時代から大学が学生に「選ばれる」時代へとシフトし、積極的な広報活動が必要となりました。
では、学生から選ばれる大学になるには、どのようなことを意識して広報活動を行えば良いのでしょうか。
ここでは、これからの大学広報に必要なことについて解説します。
オンラインを活用した広報戦略
こども家庭庁の統計によると、主要ターゲット層となる高校生の令和5年度のインターネット利用率は99.6%で、ほとんどの高校生がインターネットを利用していることがわかります。
つまり、オンラインを活用すれば、高校生の目に触れる機会も多くなり、効果的な広報活動を行うことができます。
特に今の学生は、LINE・X・InstagramなどのSNSが生活の中心にあるため、これらを活用したアプローチは必須であると言えるでしょう。
また、大学ホームページも大学に興味を持った学生や保護者は必ず目を通すコンテンツであるため、内容を充実させておくと志願者獲得に繋がりやすくなります。
高校生へのアプローチ
学生に選ばれる大学になるには、SNSの発信だけではなく、受験生となる高校生へ直接アプローチするのも効果的です。
オープンキャンパスや進路相談などで高校生が「自分が将来やりたいこと」を見つけるキャリア形成をサポートをすることで、「この大学に通いたい」と志願者の増加に繋がります。
また、在学生から高校生へ向けてイベントなどでの交流を通じて情報を発信してもらうと、入学後の具体的なイメージがしやすくなるでしょう。
効果的な大学の広報戦略のポイント
大学広報の大前提として、入学志願者を増やすことが求められますが、志願者の増加を図るには適切な広報活動を実施する必要があります。
ここでは、大学広報に効果的な広報戦略のポイントについて解説します。
大学のブランドイメージを構築する
まずは、大学の強みや魅力をアピールすることで「◯◯といえばこの大学」「◯◯を学ぶならこの大学」などのブランドイメージを構築することが大切です。
独自性のある強みや魅力を見つけてアピールできれば、受験生や保護者の興味を引くことができ、入学志願者の増加にも繋がります。
しかし、大学の考える強みと世間でのイメージが一致しないこともあるため、以下のような方法で大学に対するイメージを調査してみましょう。
- 日経メディアマーケティングの「大学ブランド・イメージ調査」を利用する
- 学生アンケートを実施する
- XやInstagramなどのSNS等でリサーチする
これらを参考に世間でのイメージに合わせた広告を打ち出せば、効果的な広報活動を行うことができるでしょう。
大学の認知度を向上させる
大学の入学志願者を増やすには、多くの受験生や保護者に大学の存在を知ってもらい、認知度を向上させる必要があります。
特に、オンラインを利用したコンテンツは多くのターゲット層に見てもらえるため、認知度の向上に最適です。
大学ホームページ内のオウンドメディアに大学の研究や学生の取り組みなどを幅広く掲載したり、SNSを投稿するなど、受験生の目に触れるコンテンツを積極的に発信することで、認知度の向上を図れます。
大学広報で重視するべきポイント
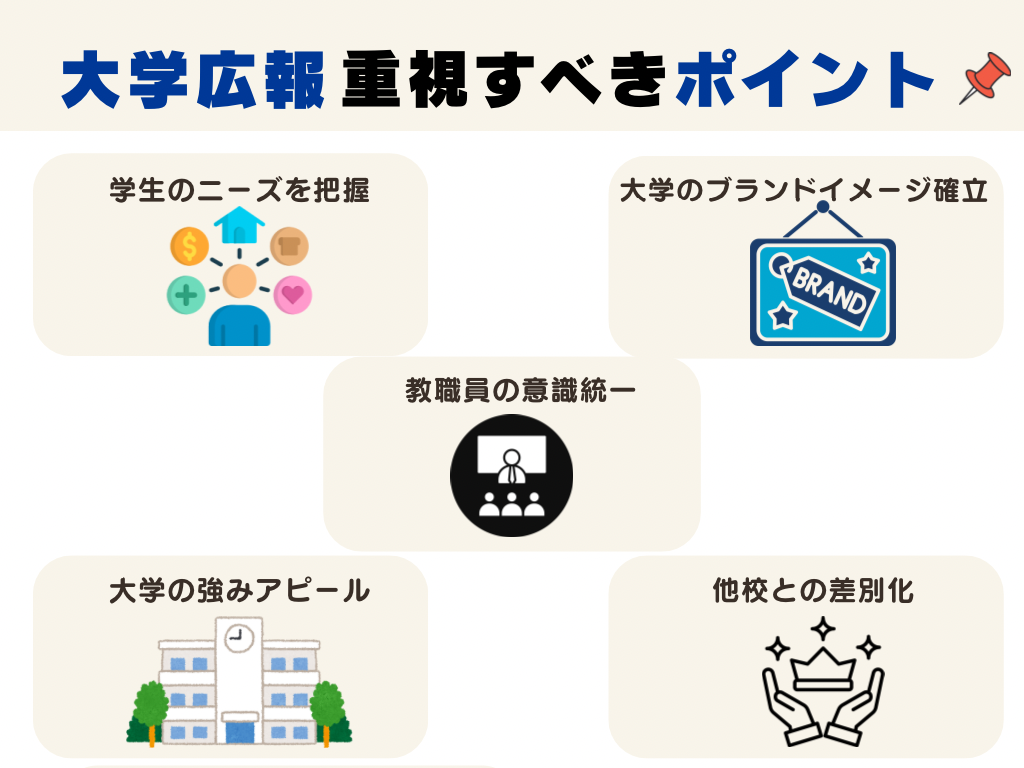
大学広報を成功させるためには、効果的な広報戦略を立てる必要がありますが、具体的にはどのようなことを意識すれば良いのでしょうか。
ここでは、大学広報で重視すべきポイントについて解説します。
学生のニーズを把握する
大学の生徒数を増加させるためには、まず学生のニーズを把握する必要があります。
どのような分野を学べるのか・卒業後の進路・交通アクセスなど、学生が大学に対して求めることは様々です。
在校生やオープンキャンパスに参加した高校生などにアンケート調査を実施すると、学生のニーズが見えてくるでしょう。
ニーズに沿った広報を打ち出すことで、入学志願者の増加に繋がります。
大学のブランドイメージを確立する
広報活動において大学ブランディングは非常に重要です。
ブランディングの一環として、イメージカラーを統一するなど、大学のブランドイメージを確立していくと良いでしょう。
Web広告やパンフレットなどの広報ツールのイメージカラーやデザインなどを統一すれば、「この大学らしい」というイメージが学生に定着します。
ブランドイメージが確立すると、学生や保護者の印象にも残りやすくなり、進路選択の際に候補に入りやすくなるでしょう。
教職員の意識統一を図る
大学広報は受験生や保護者など対外的に発信するものですが、大学内でも教職員の意識統一を行い、ブランドイメージを統一する必要があります。
学部・学科によってアピールしたい強みが異なる大学も多く見られますが、それぞれ異なる広報を行うと、一貫性がなくブランドイメージの確立は難しくなります。
大学全体でブランドイメージを意識統一すれば、大学のブランド化はより強固なものとなり、「この大学に行きたい」と、学生に選ばれる大学になるでしょう。
大学の強みをアピールする
大学広報で最も大事なことは、自校の強みを最大限にアピールすることです。
まずは、大学にどのような強みがあるのかを洗い出し、他校にない独自性のある魅力がないか分析・調査してみましょう。
具体的には、カリキュラム・キャンパス内の環境や設備・立地・卒業後の進路などで、魅力的なポイントを探します。
ただし、授業料の安さなどを強みとして打ち出してしまうと、価格競争に陥ったり、大学が理想とする学生を獲得できなくなるため注意が必要です。
他校との差別化を図る
学生に選ばれる大学になるためには、他校とは異なる強みや魅力で差別化を図る必要があります。
同じ分野を学べる有名大学や近隣大学と比較して、自校にしかない独自性のある魅力を発信することで、学生に興味を持ってもらえる可能性が高まります。
他校では学べないこと、他校では体験できないキャンパスライフなどを広報活動に活かすことができれば、入学志願者の増加にも繋がるでしょう。
効果的な大学広報の方法
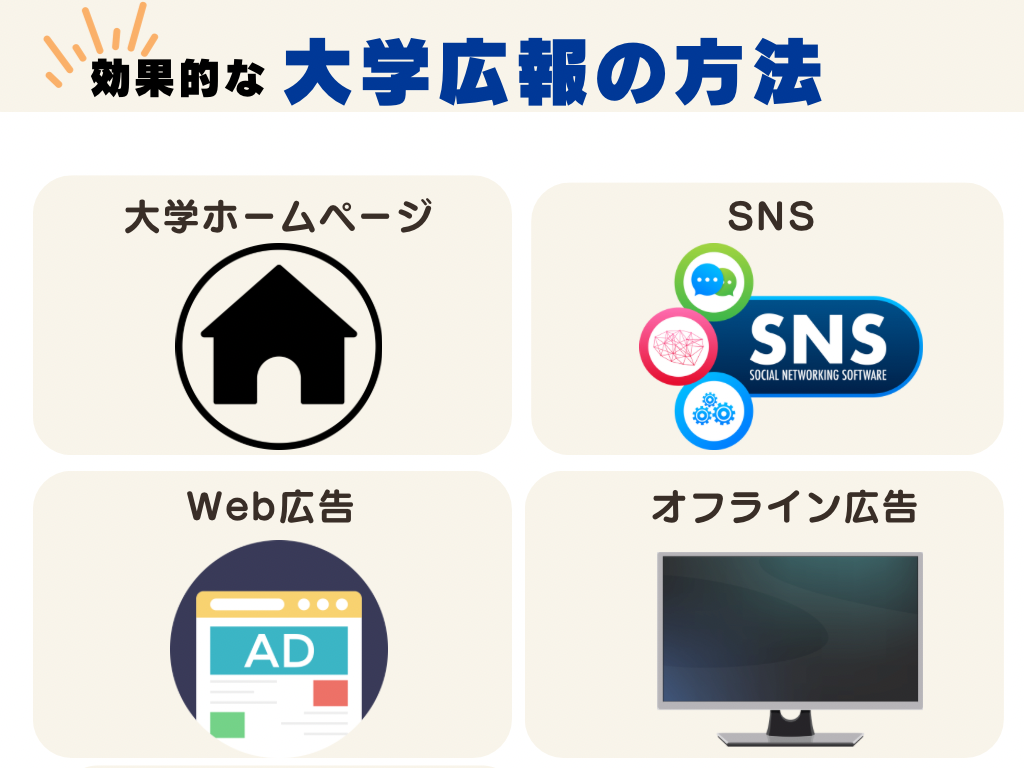
ここまで大学広報のポイントについて解説しましたが、大学広報を成功させるには広報の方法も重要です。
ここでは、大学広報に効果的な4つの方法について解説します。
大学ホームページ
学生が大学の情報収集をする際に、必ず確認するのが大学のホームページです。
大学の情報だけでなく、ブログなどのオウンドメディアを充実させるなど、自校の魅力を分かりやすく伝えるホームページを作成しましょう。
大学の雰囲気や研究結果などを発信することで、学生の興味を引くことができ、入学志願者の増加にも繋がります。
また、オープンキャンパスなどのイベントの告知も分かりやすく配置することで、学生を誘導しやすくなります。
SNS
X・Instagram・YouTube・TikTokなどのSNSは、学生の利用者も多く、広報活動に効果的です。
総務省の統計によると、令和5年度の13〜19歳の学生世代のSNSの利用率は90.3%であり、ほとんどの学生がSNSを利用していることがわかります。
また、利用目的についても「知りたいことについて情報を探すため」が63.4%と高水準であることからも、SNSを活用した広報活動は大きな効果が期待できます。
SNSには様々な種類があり、それぞれに特徴も異なるため、目的に合わせたコンテンツを利用してください。
Web広告
ほとんどの高校生がインターネットを利用している近年の状況から、Web広告は大学広報にも有効な手段であると言えるでしょう。
Web広告には様々な種類がありますが、おすすめの広告は以下のとおりです。
ディスプレイ広告:Webサイトやアプリ上に表示される画像や動画の広告
リスティング広告:ユーザーが検索したキーワードに関連して表示される広告
ネイティブ広告:一般記事などに溶け込む形で表示される広告
ただし、これらのWeb広告は費用が発生する場合があるため、費用に見合った相対効果があるかを考慮して利用する必要があります。
オフライン広告
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などのマスメディアや電車広告など、インターネットを介さないオフライン広告も大学広報に有効です。
マスメディアを利用した広告は社会的な信頼度が高く、多くの人の目に触れる機会が増えるため、集客効果が期待できるでしょう。
また、近隣エリアに電車広告を出すと、通学中の学生や通勤中の保護者の目に止まり、印象に残ることで志望校を選ぶ際の選択肢になる可能性も高くなります。
その他、近隣高校へのチラシ広告の配布も、自宅から通いやすい大学へ進学したいと考えている学生へのアプローチに効果的です。
広報がうまい大学の成功事例5選
入学志願者数を伸ばしている大学は、いずれもしっかりとした広報戦略を打ち出し、集客に成功しています。
ここでは、5つの大学の成功事例について紹介します。
近畿大学
近畿大学といえば、世界初のクロマグロの養殖に成功した「近大マグロ」のイメージを持つ方も多いでしょう。
近大マグロを前面にアピールした挑戦的な広告は、様々なアワードで賞を受賞し、広告メディア業界からも注目を浴びました。
このような広告効果もあり、近畿大学は2024年度まで11年連続で入学志願超えました。を獲得しています。
また、卒業生の有名音楽プロデューサーが演出する派手な入学式や、YouTubeへの積極的な動画投稿など、様々な施策を展開し大きな成果をあげています。
「広告ファースト」を掲げている近畿大学は、広報で成功した大学の代表例といえるでしょう。
早稲田大学
早稲田大学はすでにブランド力があり人気の高い大学ですが、オンラインでの広報活動に力を入れています。
大学広報誌「早稲田ウィークリー」は2016年4月からWebへ移行し、様々なテーマの情報を発信しており、大学情報や教授のコラムのみならず、社会的なニュースについても発信しています。
これにより、ニュースサイトなどでも記事が取り上げられる可能性が高くなり、大学への注目度がさらに高まります。
大学の規模によりオウンドメディアの効果の大きさは異なりますが、社会性のある記事を発信することで多くの人の目に止まり、集客効果が期待できます。
明治大学
明治大学はかつて、「バンカラで男くさい」という印象が強い大学でしたが、「おしゃれで明るい都市型大学」にイメージを刷新しました。
1998年に竣工された高層ビル型の校舎「リバティタワー」は都心型大学の象徴であるとも言えるでしょう。
これにより、明治大学は女子学生の取り込みに成功し、以前は8対2程度だった男女比が近年は6.5対3.5まで変化しました。
これまで取り込むことのできなかったターゲット層が獲得できたことで、2010年度・2011年度には2年連続で入学志願者数2年連続1位を獲得するまでに成長し、2025年度の入学志願者数も11万人を超えました。
このように、ブランドイメージを大きく変えて成功した事例もあります。
京都大学
京都大学は、「自由の学風」の理念に基づいて、オウンドメディアやSNSなどオンラインを活用した広報活動を展開しています。
大学情報のほか、最新の研究結果や研究者のインタビュー記事などを発信しており、さらに英語版のウェブサイトを運営するなど、世界へ向けての発信も行っています。
また、支援者(卒業生・企業)や女子学生へ向けた広報活動も積極的に行っており、幅広いターゲット層へアプローチしているのが特徴です。
特に京都大学が運営するオウンドメディアの「ザッツ・京大」は、大学の魅力の発信やブランドの確立を意識した大学オウンドメディアの好例と言えるでしょう。
青山学院大学
青山学院は、幼稚園から大学までを有する総合学園であるため、広報活動の対象は大学受験を控える高校生だけでなく、幼稚園や小中学校に通う生徒や保護者まで幅広いです。
そのため、大学が運営するオウンドメディア「アオガクプラス」は、大学情報のほかに幼児教育から高等学部向けの情報も発信しています。
このように、幼稚園から大学まで教育体制に一貫性を持たせることで、青山学院はブランド力を強化してきました。
一貫校に限らず、学内全体で意識統一を図れば、大学は成長・発展を遂げていくでしょう。
まとめ
今回は、大学広報を成功させるポイントや広報がうまい大学の成功事例について解説しました。
大学広報を成功させるには、学生のニーズと大学の持つ強みが一致しなければなりません。
さらに自校だけの独自性のある強みをアピールすることができれば、入学志願者の増加に繋がるでしょう。
また、ターゲットとなる高校生のほとんどがインターネットを利用しており、今後の大学広報においてオンラインを活用した広報活動は必須となりました。
大学ホームページやSNSなどのオンライン広告は、多くの学生や保護者の目に止まりやすく、大学の認知度を上げるためには特に有効な方法と言えるでしょう。
これらのポイントを抑えて集客に成功した近畿大学や早稲田大学などの成功事例を参考に、大学広報を進めてみてください。





