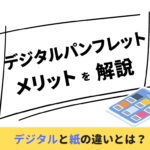2025/07/15
自校の志望者を増やす!学生募集マーケティングの基礎と効果的施策

大学や専門学校などの教育機関の職員で、学生を集めるためのマーケティングについてお悩みの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、学生募集にお困りの皆さんを対象に、なぜ学生募集のためにマーケティングが必要なのか、そもそも学生募集のマーケティングは何なのか、そしてマーケティング施策のポイントなどを解説していきます。
Contents
大学・専門学校の学生募集にマーケティングが必要な理由
まずは大学や専門学校の学生募集にマーケティングが必要な理由を、その背景からお伝えします。
学生募集における現状と課題
少子化の影響により、大学・専門学校を取り巻く環境は厳しさを増しています。18歳人口は今後も減少が続き、各校が学生確保に向けてしのぎを削る状況です。
従来型のアナログな広報手法や学校案内の配布、進路指導のみに頼ったアプローチでは成果を上げるのが難しくなってきました。
また、高校生の情報収集方法も変化しています。今の高校生世代は、InstagramやYouTube、TikTokなどを通じて学校選びの情報を得ています。
つまり、学生との接点やアプローチ手法を変えていかなければ、ターゲットである彼らに伝えたい情報が届かないのです。
マーケティング施策を導入する意義
こうした背景の中で、マーケティング的視点を取り入れることの意義は大きくなっています。マーケティングは「顧客のニーズを把握し、適切な方法で価値を届ける活動」と定義されます。
従来の広報活動に比べて、マーケティング的アプローチはより戦略的です。
つまり、データをもとに訴求対象を明確にし、チャネルを選び、施策の効果を可視化・改善することで、より効率的かつ持続可能な学生募集活動となるのです。
そもそも学生募集のマーケティングとは何か?
そもそも、「学生募集のマーケティング」とはどういったものなのでしょうか。続いてこの内容について解説します。
マーケティングの定義と教育機関への適用
マーケティングとは、顧客にとっての価値を創造し、伝え、届けるプロセスです。これを学生募集に応用すれば、受験生や保護者のニーズを正確に把握し、選ばれる学校になるための情報発信と接点設計を行うといえるでしょう。
教育機関にとっての顧客、つまり受験生、保護者、そして進路指導の教員といったステークホルダーにとっての価値とは、魅力的な教育内容、就職実績、通いやすさ、安心感など多岐にわたります。
そのため、学校は自らの魅力を的確に把握し、それをわかりやすく伝える努力が求められます。マーケティング活動は、単にパンフレットを作ることではなく、「誰に・何を・どう伝えるか」を設計するところから始まります。
学生募集におけるマーケティングのフレーム
学生募集マーケティングを進めるうえで活用できる基本フレームは以下のとおりです。
- 1.市場分析:競合校や教育トレンド、自校の強み・弱みを洗い出す
- 2.ターゲット設定:自校に合うペルソナ(具体的な人物像の水準まで落とし込んだ
想定ターゲット)を描く - 3.ポジショニング設計:競合校とどう差別化するかを明確にする
- 4.コミュニケーション戦略:使用する媒体(Web、SNS、紙媒体など)とメッセージを設計
- 5.効果測定と改善:アクセス数、問い合わせ数、来校者数などの指標をもとに改善
この一連のプロセスが、教育機関にとっての「マーケティングの実践」となります。
学生募集に有効なマーケティング施策とポイント
ここでは、いよいよ実際の学生募集に有効なマーケティング施策やポイントをお伝えします。
ターゲットと訴求軸の明確化
まず重要なのは、「誰に、何を伝えるのか」を明確にすることです。
例えば「大学所在地から離れた地方出身の進学志望者」「ゲーム業界志望の高校生」など、ターゲットを具体化することで、その人たちに響くメッセージやビジュアルを設計できます。
訴求軸についても、「就職率の高さ」や「学費の安さ」「講師の現役プロ」など、自校ならではの強みを抽出し、ターゲットにとっての価値へと翻訳して伝えることが重要です。
自校の強みを適切に把握しきれていないケースも多いですが、ターゲットと訴求軸の明確化について内部で議論する中で言語化するようにしていきましょう。例えば、ライバル校・自校と属性の近い学校と比較すると強みがはっきりしやすいことがあります。
Web・デジタル戦略の活用
受験生はスマホなどデジタルデバイスを通じて情報を得ているため、まずはWeb戦略の強化が必須です。具体的には以下の施策が挙げられます。
- ・学校公式サイトへのSEO対策整備
- ・オープンキャンパス特設サイトの設置、全ページへのCTA(Call To Action:行動喚起)ボタンの配置
- ・Google広告やSNS広告によるターゲティング広告
- ・Instagram、TikTok、YouTube、LINEといったSNSでの情報発信
こうしたチャネルで、ターゲットの興味をひく内容(学科紹介や在校生の一日はもちろん、専門課程の実習風景、課外活動など)を発信することで、認知・興味のフェーズを強化できます。
CTAボタンとは例えば資料請求や問い合わせ、イベントへの参加申込ページへのリンクボタンなど、サイト訪問者の行動につながるボタンのことです。
CTAボタンはオープンキャンパス特設サイトだけでなく、学校公式サイトの各ページにも配置するようにしましょう。
コンテンツマーケティングとブランディング
他校と差別化するためには、ブランドとしての世界観や価値観を伝えなくてはなりません。その手段としてコンテンツマーケティングが有効です。
- ・在校生や卒業生のインタビュー記事
- ・講師紹介や授業風景の動画
- ・実習・実技コンテストの成果報告
これらのコンテンツを通じて、「ここで学ぶとこうなれる」というイメージを醸成することで、志望動機の形成につながります。
記事にしても画像・動画にしても、今日の高校生はスマホを通じて良質なコンテンツに慣れていますので、なんとなく作ったような水準のものではなく、質の高いコンテンツを設置するようにしたいものです。
オフラインイベントとフォロー設計
最終的な意思決定に影響するのはイベントによる来校体験です。オープンキャンパスや体験授業は、実際に雰囲気を感じてもらう絶好の機会となります。
そして、イベントの後には必ずフォローアップを行いましょう。
- ・来校者へのLINEやメールでのフォロー配信
- ・資料請求者へのこまめな情報提供
- ・来校後アンケートをもとにした個別相談誘導
特にイベント参加者には必ず入試受付開始等の情報やリンクを載せたメールやLINE配信を行うようにしましょう。
いずれの施策でも、大切なのは行って終わりではなく効果測定と改善を行うことです。
デジタル施策はいずれもデータ収集が容易なので、学校サイトや紹介動画からの途中離脱やフォローメールからの流入といったデータを取得し、それらの改善につながるようなコンテンツの見直しを継続することが大切になってきます。
また、SNS投稿継続といった運用にはそれなりの負担がかかってきます。広報などの学校職員に負荷がかかるあまりに施策を続けられなくなる、というようなことのないよう、体制を整えることも重要です。
学生募集マーケティング施策に関する外部サービス
これらのマーケティング施策を学校内部のリソースだけで質・量とも十分な水準で行い続けることは難しい場合も多いでしょう。そこで、以下のような外部サービスを利用することも検討することをおすすめします。
Web集客・SNS運用代行
広告運用やSNS更新を内製するには時間も人手もかかります。専門の代行業者を活用することで、ターゲット設定や広告効果の最適化を図りましょう。
InstagramやYouTube運用のノウハウも提供され、成果の出やすい形での運用が可能になります。
コンテンツ企画/動画制作支援
在校生のインタビューや学科紹介動画など、プロが制作したコンテンツは訴求力が高くなります。制作会社による企画立案から構成・撮影・編集までを一括で依頼することで、質の高いコンテンツをスピーディに展開できます。
例えば、動画コンテンツであればマイナーバージョンアップを施すといった場合にも、外部制作サービスを利用していればスムーズに微調整を行えるでしょう。
マーケティング伴走支援、イベント設計・CRM自動化支援
マーケティング戦略全体の設計支援や、オープンキャンパスの導線設計、資料請求者へのステップ配信の自動化(CRMツール導入支援)などを行う外部サービス提供企業も増えています。施策の戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援を受けることで、成果を安定化させることが可能です。
コンテンツや施策のデータを取得して改善するとはいっても、具体的に離脱率や申し込み率を良くするための施策見直しをどのようにすればいいのか分からないことも多いでしょう。
そこで、ノウハウの蓄積があり、経験豊かな外部サービスを利用することで、費用対効果の高い施策を継続できると考えられます。
まとめ:学生募集のマーケティング施策には外部サービスの有効活用も検討すべき
学生募集の環境が激変する中、戦略的なマーケティングは必須となっています。自校の魅力を最大化し、ターゲットに響く訴求を設計するには、マーケティングの知見が重要です。
同時に、自前で全ての施策を行うには限界があるため、実績のある外部サービスをうまく活用したいものです。
特に教育機関の公式サイト構築の経験がある、学校の支援実績を有するなど、大学・専門学校との取引が豊富なWeb制作会社などがおすすめでしょう。