2025/03/05
大学の志願者を増やすブランディング戦略とは?成功事例も紹介
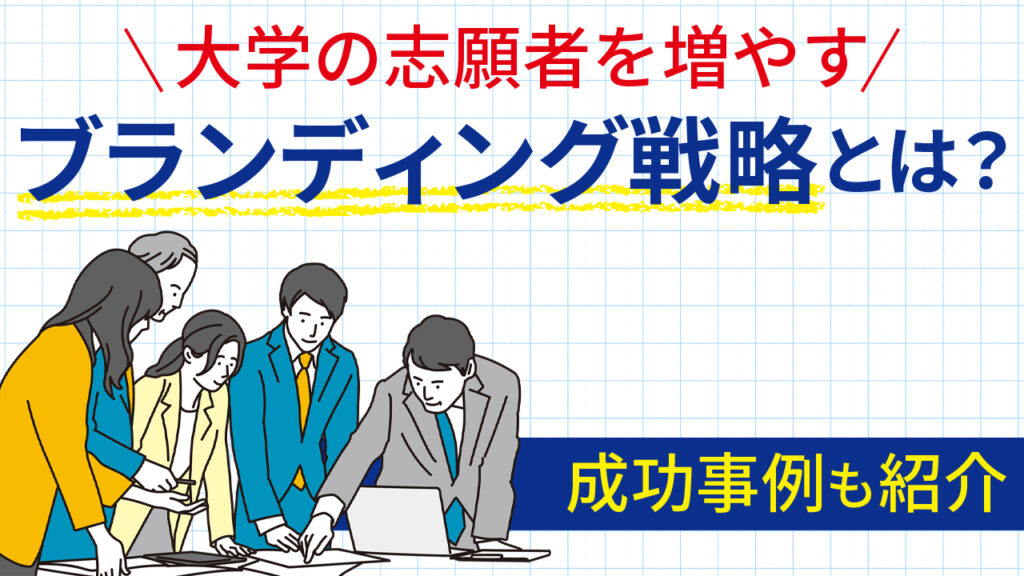
「大学への志望者を増やしたい!」
「大学をブランド化させたいけど、どのような戦略を立てたら良いか分からない」
「他の学校はどのようにブランディング戦略をしているか知りたい」
大学の志願者を増やすために、ブランディング戦略を検討している広報担当者様も多いでしょう。
本記事では、大学の志願者を増やすブランディング戦略の方法について解説します。
学校ブランディングの成功事例についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
Contents
なぜ大学にブランディングが必要なのか
少子化の進行により、学生の数は年々減少しています。
文部科学省のデータによると、2024年現在の18歳人口は2024年現在で110万人で、ピーク時の1992年の205万人と比べて約半数まで減少しています。
さらに2035年には100万人を割り、2040年には約82万人にまで減少すると推測されており、受験生の人数も減少していくでしょう。
その一方で、大学の学校数は増加しており、文部科学省の「大学進学者数に関するデータ関係」によると、4年制大学の学校数は国公立・私立を合わせて昭和40年ら317校であるのに対して、令和4年には807校と約2.5倍増加しています。
そのため、人口の少ない学生を多くの大学で取り合うことになり、学生や保護者に選ばれる大学になることが重要です。
ブランディングを確立することで競合校との差別化を図り、大学の強みや魅力を最大限に発信することでイメージの向上にも繋がります。
大学のブランディング戦略のメリット
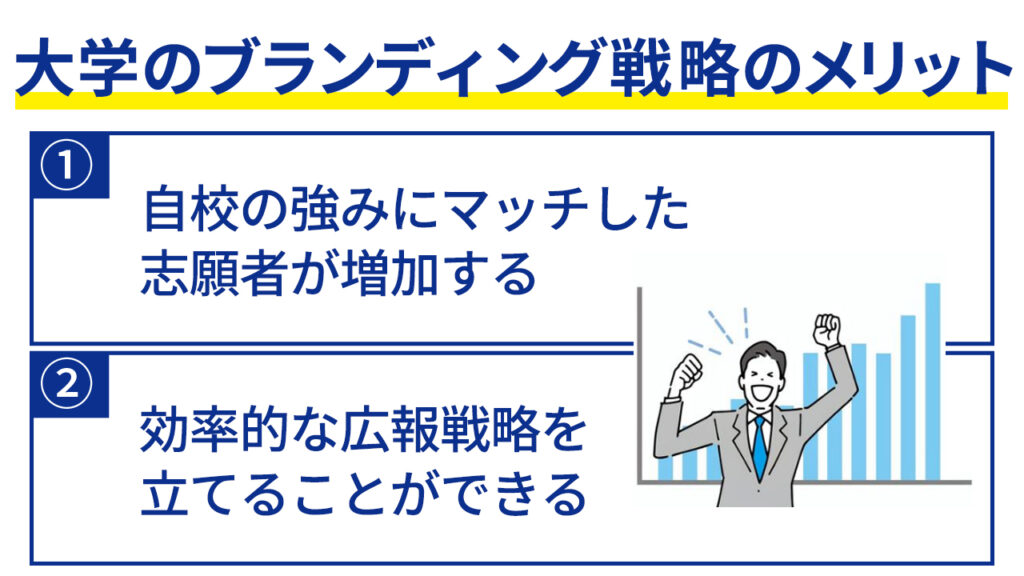
少子化や競合校の増加により、学生や保護者に選ばれる大学になるには積極的なブランディングが必要です。
ここでは、大学のブランディング戦略にはどのようなメリットがあるのか解説します。
自校の強みにマッチした志願者が増加する
大学のブランディング戦略を行うことで、「この大学では◯◯が学べる」「◯◯と言えばこの大学」などの大学が提供できる価値を学生や保護者に認知させることができます。
大学の強みや魅力を明確にすることで、学生は自分の希望に合った大学を選びやすくなり、大学が提供できる価値と学生のニーズが合致しやすくなります。
学生は大学の特徴や強みを理解したうえで大学を選択できるため、入学後のミスマッチを防げるほか、留年や退学をする生徒を減少させる効果も期待できます。
また、大学のブランドイメージを多くの人に認知してもらいやすくなり、学生を集めるのに有利な状況を作り出すことができます。
効率的な広報戦略を立てることができる
大学のブランディングを確立することができれば、それを軸に効率的な広報活動ができます。
具体的には、イメージカラーやロゴを学校案内・パンフレット・Webサイトなどの広報コンテンツで統一して利用することで、大学のイメージを印象づける方法があります。
イメージカラーやロゴを統一することにより広報コンテンツのデザインを毎回新たに考案する必要がなくなるため、その分広報活動に時間を費やすことが可能になります。
また、このようなブランディングは学生や保護者に一貫したイメージを持たせることができ、大学の特徴や強みに魅力を感じた学生を効率的に取り込むことができます。
大学のブランディング戦略の重要なポイント
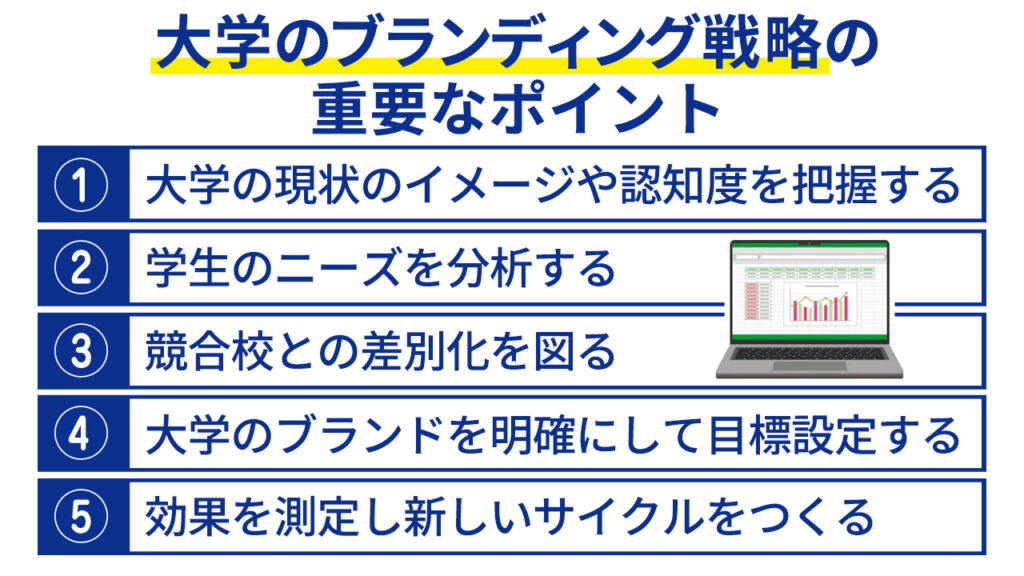
大学の志願者を増やすにはブランディング戦略を行う必要がありますが、ブランディング化を成功させるにはいくつかのポイントがあります。
ここでは、大学のブランディング戦略の重要な5つのポイントについて解説します。
大学の現状のイメージや認知度を把握する
大学のブランディングを行うには、まず大学の現状のイメージや認知度を把握しておく必要があります。
世間のもつ大学のイメージと大学が強みとして発信するアピールポイントが相違していると、効果的な広報活動ができません。
大学のイメージを調査するには、次のような方法があります。
- ・日経メディアマーケティング株式会社の「大学ブランド・イメージ調査」などを確認する
- ・在校生へのアンケート調査を実施する
- ・XなどのSNSでエゴサーチをする
特に大学ブランド・イメージ調査は自校の強みや弱み、競合校との差異などの情報収集ができるため、自校の客観的なイメージを把握することができます。
この結果をブランディング戦略に活用することで、大学の提供できる価値と学生のニーズが合致しやすくなり、志願者の増加にも繋がるでしょう。
また、大学の認知度を把握しておくことも重要です。
大学の認知度が浸透している場合は、近隣に向けては具体的な特徴や強みを発信し、遠方に向けては大学名を知ってもらうことを最優先にするなどの戦略を立てます。
このように、認知度によって広報活動の方法を使い分けることで、効率的なブランディングを行うことができます。
学生のニーズを分析する
学生に選ばれる大学になるには、学生のニーズを分析し、大学にどのような価値を求めているのかを把握することが重要です。
受験生が志望校を選ぶ際の決め手を知ることで、大学のブランディング戦略を考えやすくなり、的確なアプローチを行うことができます。
リクルート進学総研の「進学ブランド力2022」によると、高校生の進路選択における重視項目は「学びたい学部・学科がある」「校風や雰囲気がよいこと」「自宅から通える」などの項目が継続して高い推移で重視されている一方で、「教育内容のレベルが高い」「学生の学力が高い」「教育方針・カリキュラムが魅力的」などの学びの内容を重視する高校生が増加していることがわかります。
この結果から、高校生には「自分のやりたいことや夢を叶えたい」「自分のやりたいことや夢を叶るために学べれば学歴は関係ない」という価値観を持つ学生が多いことが伺えます。
したがって、大学は学生がやりたいことを学べる場を提供し、サポートできる環境を整えることが重要であるといえるでしょう。
競合校との差別化を図る
大学の学校数が増加している中で学生に選ばれる大学になるには、独自性のある強みや特徴をアピールし、競合校との差別化を図る必要があります。
差別化を図るためには、まず自校の提供できる価値・提供したい価値を明確にします。その中から競合校では提供できない価値をアピールすることで差別化を図ることができます。
ただし、学費が安いという点を差別化のアピールポイントにしてしまうと、それを目的とした学生が集まってしまい、大学が理想とする学生が少なくなってしまう可能性があるほか、価格競争に発展する可能性もあるため注意が必要です。
競合校との差別化を図るには、学習内容や施設・環境などをアピールポイントにするのが良いでしょう。
大学のブランドを明確にして目標設定する
大学のブランディングを確立させるには、ブランドコンセプトを明確にし、それに基づいた目標設定を行う必要があります。
学部によってアピールポイントが異なるなど、学内でブランディング戦略が統一されていない大学も多いです。
自校の強みや魅力として発信したいポイントや方向性について十分に議論し、中長期的に維持できるようなブランディング戦略を立てることが重要です。
ブランディング戦略を考えたら、それぞれのブランディングの項目に目標を設定します。
ブランディングの項目の具体例は、次のとおりです。
- ・ブランドコンセプトは明確であるか
- ・大学の全職員がブランドに基づく行動を行っているか
- ・他校とは異なるブランド体験を提供しているか
大学は知名度・志願者数・入学者数・偏差値などの「数値」によってブランド力を判断しがちですが、数値で判断してしまうと小規模な私立大学は低い立場に置かれてしまいます。
小規模な大学でもブランド力を向上させるには、数値以外の新たな指標を取り入れる必要があるでしょう。
効果を測定し新しいサイクルをつくる
ブランディング戦略を実施したら、その効果を定期的に測定し、結果に基づいて新しいサイクルをつくることも重要です。
効果測定する方法には、次のようなものがあります。
- ・日経メディアマーケティング株式会社の「大学ブランド・イメージ調査」
- ・インターネットモニターのアンケート調査
- ・高校生・保護者・地域住民・在校生へのインタビュー調査
これらの方法を活用して、大学の認知度はアップしているか、大学の印象やイメージはアップしているか、大学への興味が高まっているかなどを確認します。
効果が得られた施策はより拡大し、効果があまり得られなかった施策は見直しを行うなどPDCAサイクルを回すことで、より効果的な大学ブランディングを行うことができます。
大学のブランディング戦略の成功事例
ここまで大学のブランディング戦略のメリットやポイントについて解説してきましたが、どのようにブランディングを実施すれば志願者を増加することができるのでしょうか。
ここでは、実際にブランディングに成功した大学の成功事例について紹介します。
近畿大学
学校ブランディングの成功事例として有名なのが、近畿大学です。
少子化が進行し、受験生の人口が減少している中で、近畿大学は入学志願者数10年連続1位を獲得しています。
近畿大学では2008年より「広告ファースト」を掲げ、ホームページ・SNS・動画投稿・チラシなどの様々な媒体での広報活動に取り組み、ブランドを成長させてきました。
特に世界初のクロマグロの完全養殖を実現した「近大マグロ」は大きな話題を呼び、近畿大学の教育を分かりやすく伝えるコンテンツとして、現在も広報活動で活用されています。
また、公式Xを運用するなどターゲット層である高校生へアプローチする手段も取り入れており、2025年3月現在で約5万人のフォロワーを獲得しています。
明治大学
明治大学は男子学生の比率が圧倒的に高く、保護者世代には「明治大学は男子が通う大学」というイメージを持っている方もいるでしょう。
このイメージを払拭するために、ブランディング戦略によりおしゃれなイメージを加味することで女子学生の入学志願者を増やすことに成功しました。
2022年度の女子学生の人数は2013年度と比べて約15%増加しており、現在も増加傾向にあります。
また、留学にも力を入れており、2019年度の海外派遣学生数は2010年度の4.8倍まで増加しています。
そのほか、部活や研究室の情報を発信するSNSアカウントも数多くあり、各媒体でおしゃれで堅実なイメージを発信するなどして16年連続10万人の入学志願者を獲得し、学校ブランディングを成功させています。
早稲田大学
すでに世間からの認知度が高い早稲田大学ですが、SNSを利用したブランディング戦略に積極的に取り組み、ブランド力をさらに高めることに成功しています。
具体的には、XやInstagramなどの主要なSNSプラットフォームに参加し、学生・教員・卒業生など幅広いターゲット層へ向けて、大学のイベント・セミナー・研究結果・その他学生の活動など、多岐にわたるコンテンツを提供しています。
SNSに様々なコンテンツを発信することで、大学に興味を持つ人々にアピールしブランドの多面性を示すことができます。
まとめ
今回は大学の志願者を増やすブランディング戦略の必要性やメリットについて解説しました。
少子化の進行や大学数の増加により、大学が学生を「選ぶ」時代から大学が学生に「選ばれる」時代へとシフトしています。
そのため、大学は志願者を増加させるために積極的なブランディング戦略を立てて広報活動に取り組む必要があります。
大学のブランディング戦略を考える際には、大学の提供できる価値と学生や保護者のニーズを合致させる必要があり、さらに競合校との差別化を図ることも重要です。
それらに基づいてブランドを明確化し、効率的な広報活動を行うことができれば、志願者の増加に繋がるでしょう。
以上を参考に、自校に合ったブランディング戦略を考えてみてください。





